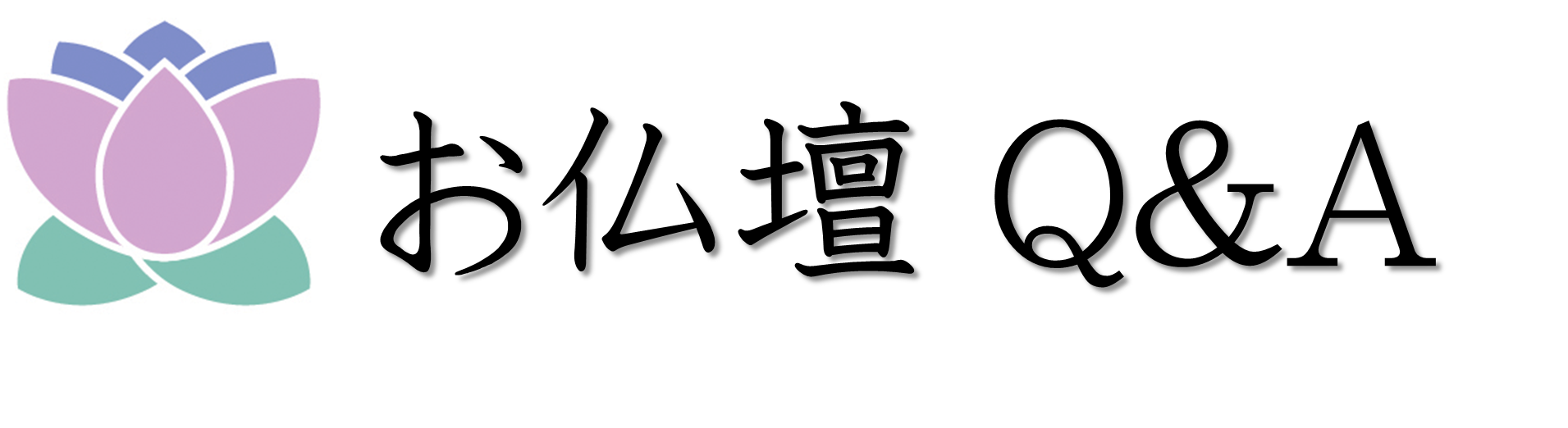
-
お仏壇は、なんのために祀るのですか?
-
お仏壇は信仰の中心となる「御本尊」をお祀りする家庭の小さなお寺です。
また亡くなられた大切な方やご先祖様と対話をしたり、日頃の感謝を伝えたりするための大切な場所です。ご供養を通じて日々の心のよりどころとなることでしょう。
-
お仏壇を買い替えるのですが、古いお仏壇の処分はどうすればいいですか?
-
新しくお仏壇を買ったとき、誰でも頭を悩ますことは、古いお仏壇をどう扱うかです。
まず、お寺にお願いして「魂抜き」・「み霊抜き」と呼ばれる儀式をとり行うことが必要です。
そして魂抜きをしたお仏壇は、当店で引き取り、お焚きあげ(焼却)させていただきます。
- お仏壇はいつ購入するものなのですか?
-
身近な方が亡くなった場合、四十九日法要までに購入するとよいでしょう。じっくり考える余裕がなかった場合などは、一周忌などに合わせて購入するのもひとつの方法です。その他、家の新築・引っ越し・買い替えなどお仏壇の購入を考えるタイミングは様々です。
お仏壇を購入するのに良い時期、悪い時期はありません。お仏壇をご安置したいと思われたその時が最良の日と言えるでしょう。
- 練り物と調物(張り)の違いは?
-
一般的に唐木仏壇の場合は、練り製品と調物(張り)製品の二種類があります。
『練り製品の場合』
唐木仏壇のほとんどは、唐木だけでできているわけではありません。
木材の反りを防ぐために、別の木を芯材に使い、厚さで六mmから七mmの板を張りつけて作ります。これを『練り工法』と言いますが、前面に張りつけているもの、側面や裏側にまで貼りつけているものもあり、唐木の使用量が多いほど高価なものになります。
『練り工法』のものに、前練り・二方練り・三方練り・四方練り・総無垢造工法などがあります。『調物(張り)製品の場合』
調物(張り)製品には、やや厚めの紙ほどにスライスした唐木を張ったものや、木目をプリントした化粧合板タイプの製品(低価格の家具などに多く使われています), 木目を白木に転写した材料を使った製品などもあります。
芯素材・芯材のみ・突板張り工法などがこれに当たります。
-
お仏壇の価格を決めるのは?
-
デザイン性などの価値を除き、材料となる木の種類と使用量といえると思います。
同 じ木材でも良いものとそうでないものがありますから、一概には言えませんが、銘木と呼ばれる黒檀や紫檀、桑、ウォールナットなどの木材であれば、一般的に高額になります。
しかし木材は、木肌がどんなに美しい銘木でも、天然木である以上、板に反りや縮みなどがあり、繊細さと精巧さが求められる仏壇や家具には、本来難しい素材といえます。
そこで考えられたのが、芯材には反りや縮みが少ない合板(天然木化粧合板)を用いるという方法です。
加工技術に芯素材・芯材のみ・突板張り・前練り・二方練り・三方練り・四方練り・総無垢造工法などの工法があり後者になるほど高度な加工技術や大量の銘木が必要となるため、高額になります。
一般に最高級品といわれる「総無垢」は、「年月と共に味わいも増す」と言われます。
大切な事は、一生のうちで、あまり買い換える事のない仏壇ですので、愛着の持てるものを探し、品質を理解し、その特徴・価格に納得して購入する事ではないでしょうか。
- お仏壇の掃除は毎日必要ですか?
-
『唐木仏壇』
仏壇の掃除はハタキで優しく埃を払い、柔らかい布や仏壇用クロスで拭き取ります。市販の化学雑巾は変色する恐れがあるので、なるべく避けましょう。汚れが落ちにくい場合は、ぬるま湯に浸した柔らかい布を強く絞って拭きます。仏壇は湿気が大敵。水気を残さないようにしっかりと乾拭きを。仏壇に水をこぼした場合、乾いた布ですぐに拭き取ります。本尊や位牌は、ハタキでほこりを払います。
『うるし塗りの部分』
やわらかい植物性繊維(ガーゼや綿布など)を使用して空拭きしてください。かたい繊維では傷がつくことがありますので注意が必要です。
傷の原因になりますので花瓶や仏飯器など固い仏具は直接うるし部分に当てないようにします。
うるしは元来水分には強いのですが、下地に砥の粉、胡粉を使ったものが多く、多少の傷から下地に水が浸透することがあります。たとえば、花瓶の裏に水で濡れていますと、うるしの塗りがはげてきます。
花瓶の裏を乾いた布でよく拭いてからお供えしてください。『金箔部分』ほかの部分と違って、拭いては絶対にいけません。金箔は軽くほこりを払うだけでよいのです。ほこりが取れない複雑な部分は毛筆の先をほぐしてから払ってください。金箔は手で直接触ると指紋がつき、それをこするとはげてしまったりしますのでご注意ください。『金物・金具』お仏壇の扉などに使われている金物や金具は塩分を嫌います。汗ばんだ手で触ったりしないようにご注意ください。
『ご本尊・お位牌』自己流に手入れをするとかえって傷めることになります。
汚れがひどくなったら当店にご相談ください。※お仏壇は湿気・直射日光を嫌います。梅雨時など湿気が多い日が続いたときには天気の回復を待って窓を開いて風通しをよくしてください。
なお、お手入れをする前後には必ず合掌礼拝をします。
-
お仏壇の耐久年数はどのくらいですか?
-
お仏壇の耐久年数は普通50年くらいと言われています。しかし、お手入れや仕様によっては当然変わってきます。
実際、300年、500年とお参りし続けれてきた素晴らしいお仏壇もあります。すす抜き、塗り替えを定期的に行うだけで耐久年数はだいぶ違います。また安置する場所によっても変わってきます。
湿気の少ない所に安置することで長持ちします。

